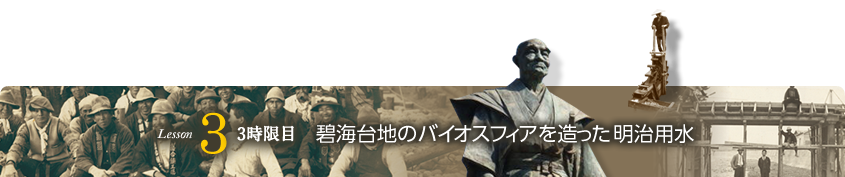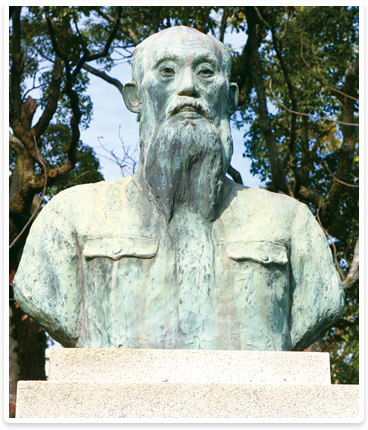正解 C 用水を掘 ること千里、その恩恵 は万世におよぶ
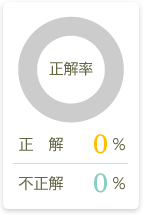 明治用水が完成してからこの
明治用水が完成してからこの碧海 台地の発展ぶりは著しいものとなりました。明治18年(1885)にはすでに5,000ha近い水田が開墾 され、明治後期には8,000haを超 す一大穀倉地帯へと変貌 をとげたのです。
さらに同34年(1901)、安城農林学校(現高校)初代校長として赴任 した農聖山崎 延吉 は、米を中心に畑作、養鶏 、養蚕、果樹と多角経営を指導し、その隆盛 ぶりは「日本デンマーク」として全国に鳴り響 いたのです。視察者が次々と訪れ、安城駅前には旅館、食堂、演芸場、映画館などが立ち並びました。
戦後の経済成長期になると、明治用水を利用した「西三河工業用水」が造られ、この地域は愛知工業王国の一翼 を担うこととなります。新幹線の駅もでき、安城市は農業と工業が共存する街として人口18万人の中核 都市へと発展を遂 げたのです。
先人が造り上げた明治用水は、通水130年を経た今も安城の地に莫大 な恩恵 を与 え続けています。まさに「利澤 萬世 (恩恵 は永遠に続く)」ですね。
正解 C 用水を掘 ること千里、その恩恵 は万世におよぶ