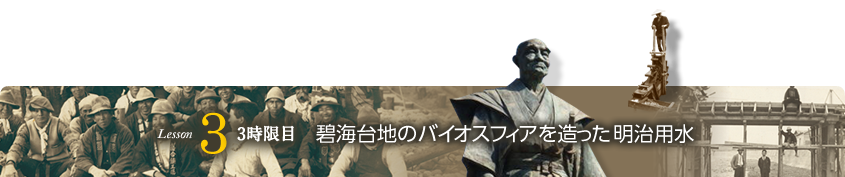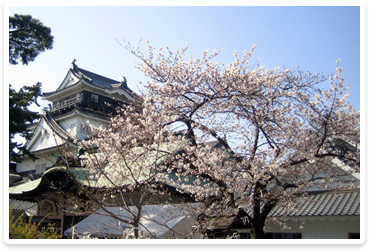正解 C 岡崎藩 と同じ5万石
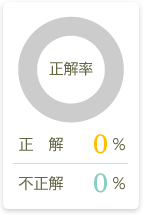
都築弥厚 の計画では、この水路を引くことによってできる新しい田んぼは4,200ha、約5万石の収穫 高と計算しています。
幕末当時の三河の主な藩 は吉田 藩 (豊橋)7万石、岡崎 藩 5万石、刈谷 藩 2万3千石、挙母藩 (豊田)2万石ですから、キツネしか住まなかった荒地 が、たった一本の水路で5万石という岡崎 藩 と同じ収穫 高が得られる穀倉地帯へと変貌 することになります。
都築弥厚 の計画は失敗しますが、その夢は維新 後に明治用水となって実現します。明治用水によって碧海 台地には8000ha以上の田んぼができたのです(明治40年(1907))。
石高に直せば実に10万石以上。江戸 時代であれば、三河で一番大きな藩 ができたことになります。
正解 C 岡崎藩 と同じ5万石